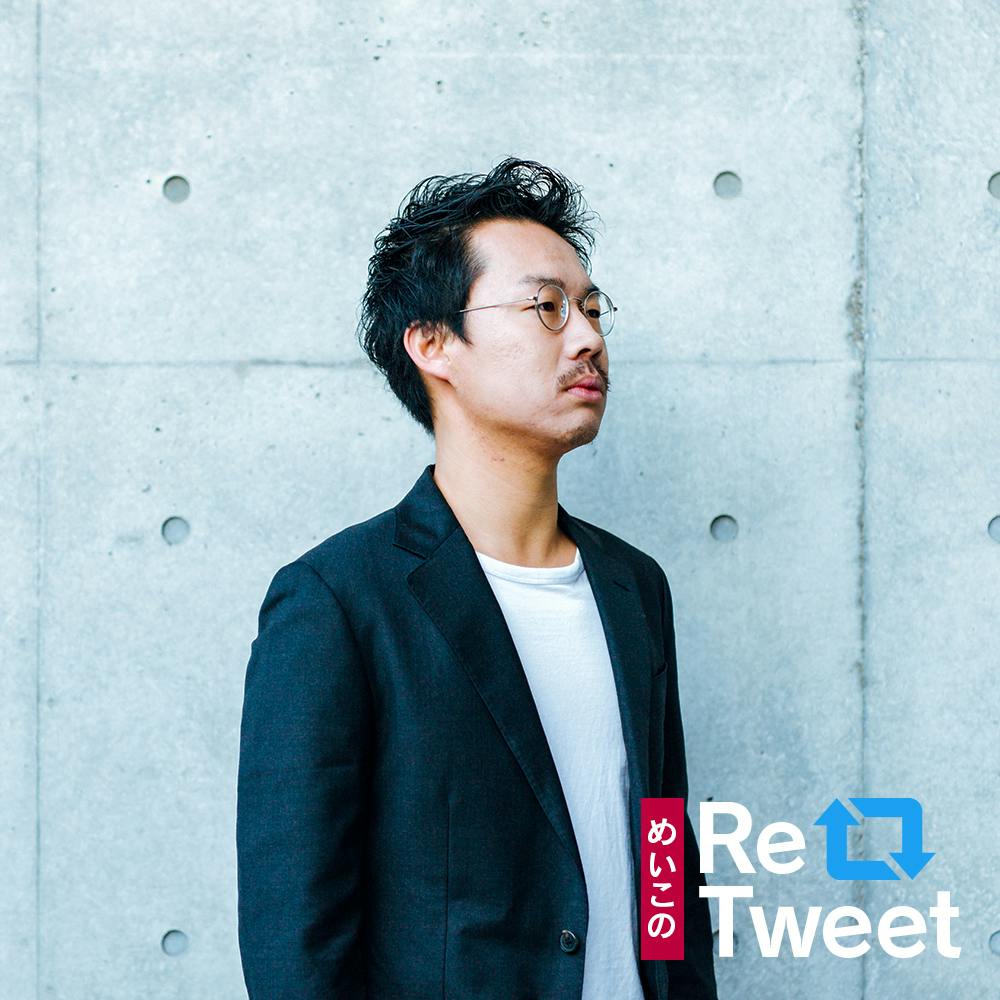こんにちは、ワンキャリ編集部のトイアンナです。
これまで400人程度の学生に就活指導をしてきた中で、頻繁に受けた質問の1つが「面接の通過方法」です。企業ごとに面接対策が異なることも事実ですが、今回はどの企業へエントリーする際にも基本となる「採用担当者の視点で考える」対策方法を回答したいと思います。
<目次>
●採用面接官が応募学生に対して気にしているのは何か
●1次面接の採用面接官が怖いのは「怒られる」こと
●採用面接が進むほど見られるのは、「相性」
●段階別に面接対策をしよう
●面接を通じて成長しよう
採用面接官が応募学生に対して気にしているのは何か
まず、応募企業の採用面接官がどういう人なのか考えてみましょう。人気企業であれば応募者が数万人なんてこともザラです。筆記試験で絞り込みをするといっても、最低数百人の採用面接を行う必要が生じます。
これら数百人分の採用面接を担当しているのは、企業の誰でしょうか?
数百万人の応募学生全ての採用面接を、企業の人事部が担当しているわけではありません。人事部は企業の各部署の社員に採用面接官を担当するように依頼し、彼らに今年の採用方針などをあらかじめレクチャーします。つまり、採用面接官の大半はあなたがOB・OG訪問で知り合うような普通の会社員なのです。
1次面接の採用面接官が怖いのは「怒られる」こと
そんな「1日面接官」の企業社員は、何を考えているでしょうか?
面接は一般的に、進むほど「年次が高く」「地位が高い」社員が担当します。1次面接は入社数年目、2次面接は課長クラス、3次以降は人事と部長クラス……といったように担当する役職が上がっていく場合が多いです。もしあなたが1次面接官だったとしたら、何を考えるでしょうか?
私が実際に面接をサポートしたときに考えたのは「変な応募学生を次の採用プロセスに通して、偉い人から叱(しか)られたらヤダなぁ」でした。
面接官も普通の会社員。優秀な学生を取りこぼしても他社に内定されるだけで済みますが、ダメな学生を通過させてしまうと「なんでこんな学生を次の面接に回したんだ」とお叱りを受けるかもしれません。
従って、面接担当者は「最高の学生を取る」ことより「最低の学生を次のプロセスへ通さないこと」を目標にします。つまり裁量が小さな社員が担当する初期の採用面接ほど、個性よりも無難に優秀さをアピールすることが、面接対策の正攻法です。
採用面接が進むほど見られるのは、「相性」
しかし、面接官の質問に対して、最初から最後まで無難な回答だけをしていてはいけません。なぜなら、それは年次が上の面接担当者になればなるほど、単なる優秀さより、企業とのエモーショナルな相性を確認しているからです。
「この子は優秀な学生さんだけど、なんとなくウチの会社にいるイメージが湧かない」
「ちょっと不器用なところはあるけれど、弊社で仕事していそうな気がする」
このように最終面接や役員面接に近づくほど、感情や相性で採用可否を判断される範囲が大きくなるのです。
段階別に面接対策をしよう
ここまで、企業の採用面接にはさまざまなフェーズがあることをお伝えいたしました。では、具体的にどう面接対策をすべきでしょうか? 私は「面接段階で分けた対策」を行うべきだと回答します。
1次面接~選考中盤
- 自分の優秀さを全面にアピールするようなエピソードを準備する
- 大学のGPAスコアや研究分野の簡単な説明文など、自分の学業に関する情報を頭に入れておく
- 外資系企業を受けるならフェルミ推定、ケース面接対策の過去問を解いておく
- あなたを動物にたとえるなら? といった瞬間的な頭の回転を問う質問に回答する練習をする
<実際に答えられるようにしたい質問例>
「学生時代に頑張ったことは何ですか?」
「自分の強みとそれを実証するエピソードを教えてください」
「あなたは周囲の人からどんな人だと言われますか?」
「あなたの大学でのGPAスコアはいくつですか? そのスコアを自分の中でどう捉えていますか?」
「あなたを魚にたとえるなら何ですか? その理由は?」
「デスクトップパソコンの市場を今の1.5倍に拡大したいならどうすべきですか?」(ケース面接)
「日本中にあるペットボトルの数を5分以内に概算して回答してください」(フェルミ推定)
選考中盤~最終面接
- 志望動機に自分の感情も絡めて説明、回答できるようにする
- 企業が採用時に求める人材の典型的な性格を分析し、自分が合致する点をアピールする
- 面接後のお礼や気遣いなどで、面接官の受ける印象に差をつける
実際に回答できるようにしたい質問例
「仮に業界1位の◯◯に内定しても、あなたは弊社を選びますか。それはなぜですか?」
「あなたが弊社を第一志望にした経緯は何ですか?」
「弊社について知っていることを何でも教えてください」
「あなたはどういう理由で、自分が弊社に合う人材だと考えましたか?」
もしも応募企業が求める人材をうまく分析できないときは、別ページでご案内している「Big Five」という型を使ってみてください。この分析は人材を「外向性」「情緒安定性」「開放性(好奇心の強さ)」「勤勉性」「協調性」の5つで判断するもので、実際に採用の現場でも利用されているものです。
面接を通じて成長しよう
ここまで、面接対策の基礎として、採用面接官が何を考えているかという視点から、段階別の対策をお伝えしてまいりました。特に準備が必要なのはエモーショナルな志望動機作りですが、もし現時点でしっかりした応募動機が作れなくても問題ありません。
最初はエモーショナルな応募動機がない場合も、面接を経て志望度が上がることはよくあります。選考を受けながら企業をしっかり調べ、最終面接や役員面接までに企業の採用面接官が「これなら内定をあげたい」と思える人材へ成長していってください。
※こちらは2016年4月に公開された記事の再掲です。
▼このカテゴリーの他記事はこちら
▪️面接対策一般 ・【面接前日に確認!】思わぬ質問からの失敗を防ぐ5つの準備・対策法
・面接で求められている「コミュニケーション能力」って何?面接で見られる2つのコミュ力とは
・【面接対策】テンプレ付き「模擬面接」のすすめ:たった1時間で通過率アップ!?
・集団面接|流れやマナー、質問例など受かる人のコツや対策法を網羅
・面接で自己紹介を成功させたい!伝えるべき4つの内容と7つのポイントを回答例も交えて解説
・面接時間の平均は?短いor長い場合は不合格?採用の裏側を整理
・「なぜか面接で落ちる」君が知らない、7つのNG行動チェックリスト
・圧迫面接とは?具体例や企業側の意図・NG行動から対策まで徹底紹介!
・人事は「超優秀だが、逃げる学生」と、「彼より劣るが、自社に確実に来る学生」どちらを採るべきか?の二律背反で悩んでいる【キャリア相談】
▪️質問対策 ・こいつはヤバイ、就活生の生死を分ける「キラー質問」。面接で生き残るための回答例とは?
・【学生時代に力を入れたこと:面接対策編】就活でよく聞かれる質問「ガクチカ」
・【面接対策】短所に関する質問の意図と正しい回答とは?例やエピソードを交えて解説!
・「他社さん、どこ受けてるの?」に正直に答えてはいけません
▪️逆質問 ・【逆質問の例一覧】面接官の意図は?就活生におすすめの質問/聞いてはいけないこと
・【面接の逆質問】厳選14例|業界別&選考フロー/面接官別の鋭い質問
▪️フェーズ別面接対策 ・1次面接の対策!よく聞かれる質問と落ちる人の特徴を詳しく解説
・二次面接では何を聞かれる?質問への回答例と対策を解説!
・最終面接で落ちる理由と対策|合格率を高める志望動機/逆質問/自己PR
・最終面接で聞かれる質問は?受かるための対策方法と回答例を紹介
▪️マナー ・【就活メールの例文&マナー】正しい書き方とテンプレ集(面接/OB・OG訪問の日程調整/お礼/辞退連絡など)
・就活生が押さえておきたい面接のマナーを徹底解説!
▼選考対策総集編記事一覧
・【26卒向け】インターン/就活はいつから?スケジュールと準備の進め方
・OB・OG訪問とは?就活でOB・OG訪問が必要な人、しなくていい人
・志望動機の書き方と例文集|人気8業界のES通過例文 と王道の回答例
・【自己PRの書き方】ESで強みを効果的にアピールするには?新卒採用担当の目線と内定者の回答例から解説
・【面接対策】質問集&回答例|新卒就活でよく聞かれることと準備方法
・【自己分析のやり方】たった4通り!簡単にできる方法・ツール・シートを解説
・【業界研究:34業界収録】めんどくさい業界研究は全て任せろ!金融/商社/不動産/メーカー/広告/コンサルなど人気業界/企業を徹底比較
・【Webテストとは】主要9種類を網羅!適性検査の特徴、対策本、出題企業一覧
・グループディスカッション完全対策!全テーマの進め方/コツや役割を網羅的に解説
・ケース面接対策&例題|コンサル・日系大手も出題!ゼロからの始め方
・ESの書き方&例文集|エントリーシートの基礎から質問別/業界別の回答例まで完全対策








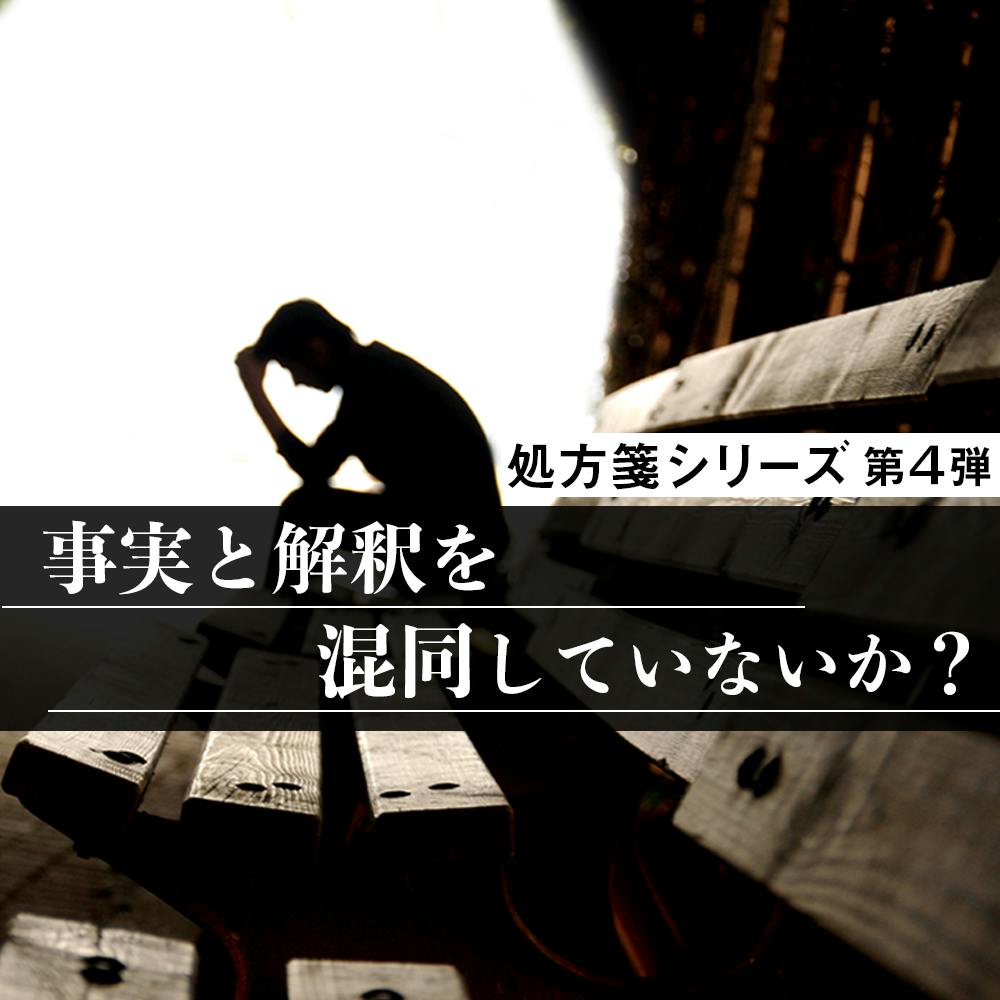
.jpg?ixlib=rails-3.1.0&auto=format&fit=max)