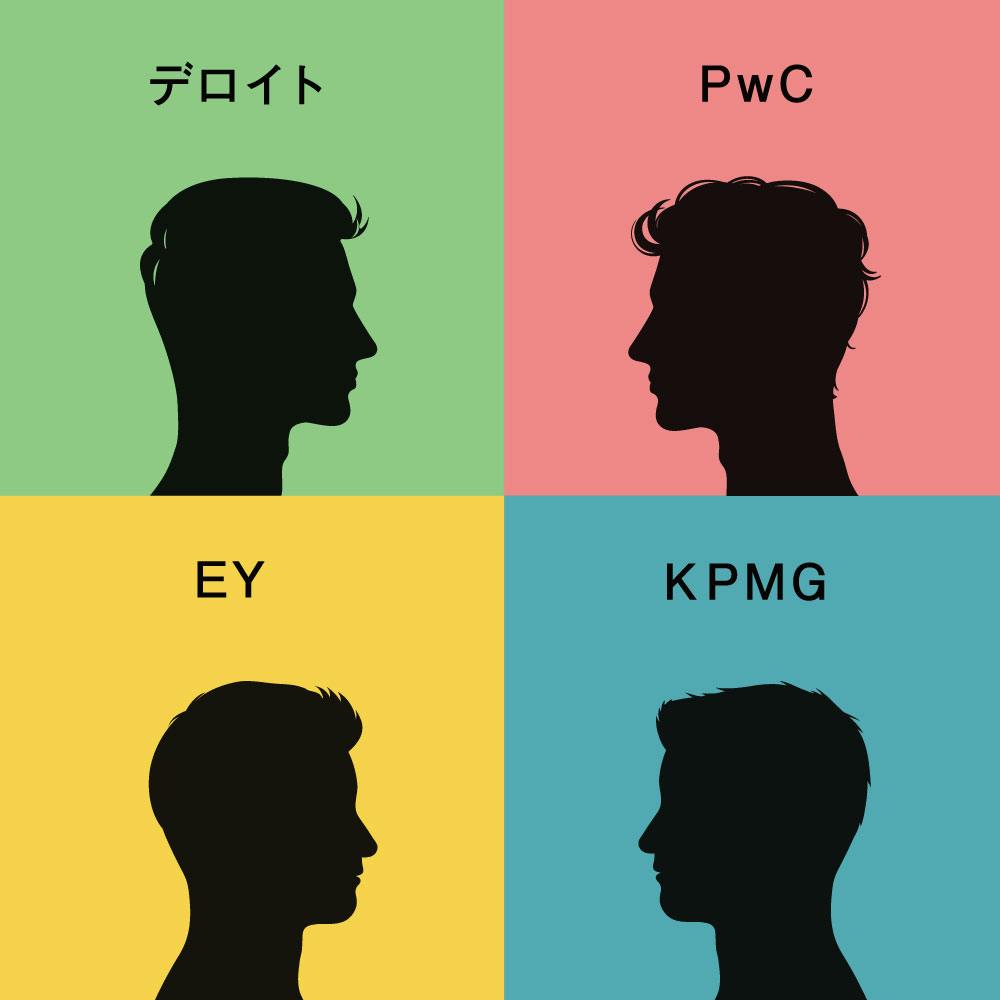「今、商社は大人気で『ストップ高』のような状態。そこに入ろうとするなんて、センスがないと思いませんか?」
こう学生に問いかけるのは、Shippio代表の佐藤孝徳さん。自身も商社に新卒入社した身だからこそ、この言葉には重みがある。
三井物産に10年間勤めたのち、同僚と起業し、Web上で輸出入の発注、管理ができるサービス「Shippio」をリリース。ANAグループと業務提携し、累計で13億円以上を調達するなど、各方面から注目を浴びている。
国際物流や起業に関する情報をTwitterで発信する、物流太郎(@LOGITARO1)としても活躍している佐藤さん。商社に10年勤めて分かった、商社を喰う人、そして喰われる人、そして「今、商社を選ぶ学生はセンスがない」と断言する理由に迫った。
佐藤 孝徳(さとう たかのり):株式会社Shippio代表
1983年生まれ。新卒で三井物産に入社。石油部での原油トレーディング業務、企業投資部にてPE投資・スタートアップ投資業務などを経て、中国総代表室(在北京)にて三井物産の中国戦略全般の企画・推進を行う。2016年6月、北京で同じく駐在していた土屋氏とともに、国際物流スタートアップ「サークルイン株式会社」(現・株式会社Shippio)を創業。
今「ストップ高」の商社を選ぶことに、センスのなさを感じる
──本日はよろしくお願いします。いきなり本題なのですが、以前のインタビューで佐藤さんは「人気だから商社に行くという学生は、その時点でイケてない」と発言されました。その真意について、もう少し詳しくお聞かせいただけないでしょうか?
佐藤:商社パーソンの基本は、安く売られているものを見つけて買い、それを高く売ってもうけることです。今、商社は大人気で「ストップ高」のような状態。既に高値になっている、つまり成長のほぼ終盤に来ている会社を選ぼうと考えること自体、商人あるいは事業投資家としてはセンスがないことだと思いませんか?
──冒頭からなかなか手厳しいご意見です。今は「センスがない人」が商社に集まっているということですか。
佐藤:そんなことはないと思いますが、ぶっちゃけ「アンテナが低くて、頭がいい人」というのが、今の商社パーソンのボリュームゾーンでしょう。出来上がったシステムをうまく運用しながら、延々と持久走ができる人というイメージです。逆に事業をゼロから作れる人は、商社にほぼいないと思います。プライドが高い商社の人たちは認めないと思いますが。
──そうなんですか? 事業投資なども行っていますし、起業との親和性が高いと思っている学生は少なくないと思います。
佐藤:6を9にすることは得意だけれど、1から5にするのはそれほど得意ではないし、ゼロから何かを作るという経験を持っている人はほとんどいないという印象です。
私よりもっと前の時代の人、それこそ、総合商社にまだベンチャーマインドが残っていた頃の人は0からやった経験をたくさん持っていると思うのですが、今いる人には、その機会も戦闘能力も残っていないんじゃないでしょうか。
──昔はあったのに、なぜ0から作る能力がなくなってしまったんですか?
佐藤:商社が扱っているものが変わったからだと思います。例えば、資源ビジネスで大きな金額を稼げるようになってしまったことで、コンシューマービジネスやスタートアップに近い、0から1の立ち上げリスクを取るメリットが相対的に薄れてしまった……みたいな話です。
──では0→1をやりたいと思っている人に、商社は向かない?
佐藤:怒られることを覚悟で言いますが、ほとんどの商社パーソンにとってベンチャーをゼロから立ち上げるのは難しいと思います。なぜなら、彼らにはプロダクトを作った経験もなければ、ゼロから泥臭い営業をして数字を追いかけた経験もないからです。
──起業だけでなく、商社パーソンにはベンチャーを経営する能力もないと思いますか。
佐藤:すでに規模が大きくなっている海外企業が、日本展開をする場合のカントリーマネージャーなどには向いているかもしれません。リソースがある程度潤沢にあった状態で、物事を回す経験は積んでいると思いますから。
やりたいことを「全て」やらせてもらえた商社には、感謝しかない
──なるほど。確かに「今」選ぶ理由としては、商社は弱くなっているのかもしれません。とはいえ、佐藤さん自身、新卒で三井物産に入社されていますよね。それはなぜですか?
佐藤:私は就活をする前に、ベンチャーのファンドでインターンをしていたのですが、そこで「商社は100人いる同期が世界中に散らばっているような環境。同期が数人しかいない会社よりも、10年後に世界が広がるのではないか」と助言されたことをきっかけに、商社へ行くことを決めました。
──そうだったんですね。ベンチャーを選ばなかったのには、他にも理由があるんですか?
佐藤:当時はライブドア事件が起きたこともあり、ベンチャーを懐疑的に見る人が多かったと思います。また、資金調達の手段やボリュームも限られていました。
時代はそれこそ、外銀や外コンがもてはやされていて、商社も人気ではありましたが、そこまで盛り上がっている雰囲気は感じませんでした。単純に海外に行くチャンスが多そうで「面白そうだ」と思った記憶があります。
──「10年後に世界が広がる」。そう言われて商社に入った佐藤さんですが、実際に商社に入ってみてどうでしたか?
佐藤:原油のマーケティングやトレーディング業務に始まり、スタートアップ投資、中国駐在などを経験しましたが、商社時代の配属は基本的に希望した部署に行かせてもらいました。海外にいる志の高い経営者や優秀な先輩にも出会えましたし、やりたいことを全てやらせてもらえたので、本当に感謝しかありません。
私が商社を辞めたのも、次に商社でやりたいことがあるかと考えたら、強く望むものがなかった、というのが大きな理由です。ただ、シンガポールや上海、アメリカなど世界中に同僚がいて、辞めた今でも旅行や出張をした際に情報交換ができます。そう考えると、今の方がより商社に入った価値を感じているかもしれません。
──佐藤さんから見て、商社で身につくスキルは何だと思いますか?
佐藤:まとめるとコミュニケーション能力が高くて、調整能力があり、PLやBSが読めて、最低限の契約に関する法律の知識があるような人材になれるというところでしょうか。レポーティングなど、仕事における基本的な能力も大きく高まると思います。
私自身は駐在なども経験させてもらい、グローバルな視点を得られたと思いますし、会社のお金でいろいろな国に行けて、他言語も勉強させてもらえるという点は商社ならではのメリットだと思います。
──商社を辞めて起業してから、これは役立っているという知識はありますか?
佐藤:ないわけではないんですけど……。今パッと思いつくものはないですね。
──そうでしたか(笑)。希望の部署に移り続け、そのまま商社に残るという考えは、佐藤さんにはなかったのでしょうか?
佐藤:三井物産の経営に携わってみたい……と考えたこともあります。ただ、そこにたどり着くにはさらに20年以上かかります。そこまでは待てないと考えました。
総合商社はバケモノ。その有機体の血肉となるか、新たな生命体を生み出すか
──例えば、佐藤さんの今の経営者としての経験を生かして、「もう一度商社で働いてみないか?」と誘われても戻ることはないですか?
佐藤:それはないかな……。これは私が在職中に勝手に思っていたことなんですが、三井物産は140年以上生きてきた生物、ある意味バケモノとも言えます。イメージとしては、社長が脳で、取締役たちが臓器で、社員がそのほかの細胞という感じ。
中の人が入れ替わることで、新陳代謝はしているのだけれど、何のために働いているのかといえば、この三井物産という巨大な有機体を生存させるためだな、と感じることがありました。伝わるかな……。
──会社を存続させることが、事業の目的になってしまっていると。でもそれは、商社だけでなく、大企業の多くに当てはまることかと思います。
佐藤:確かにおっしゃる通りです。ただ、商社ってこじらせやすいんですよね。給料はいいし、モテるし。サラリーマンとしてのヒエラルキーの一番上に自分がいると感じている人も多くて、上から目線のクセがついてしまっている人も少なくありません。ベンチャーとの事業提携を担当する社員が、そんな横柄な態度だと起業家はイラッとしますよね。私もそんな経験が何度かありました(笑)。
──なるほど……。「プライドが高い」というような話は、この特集の取材で何度も聞きました。
佐藤:入社して3年くらいまでの方が、頭がフレッシュで違和感を覚えることが多いと思います。でも、皆さんがおっしゃっている通り、いつの間にか飼いならされてしまう人が多いのは事実です。
一方で、誤解してほしくないのは、特にベンチャー界隈(かいわい)は「商社マンうぜぇ」と言いがちなんですけど、こんなすごい組織はなかなかないです。
──と言いますと?
佐藤:年収を平均1300万円社員に支払い、駐在の家賃や教育費、駐在手当などをすべて払って、出張もビジネスクラスで飛んで、滞在先のホテルも高級で、さらにあらゆる税金を払っても、年間で税引後利益4000億円を稼ぐんですよ? そんな事業を、ベンチャー界隈で作れている人はまだいません。
こんな風に言ってますけど、もちろん、本当に優秀で残っている人もいます。そういう人は三井物産で偉くなっていくでしょうし、偉くなって世の中を大きく変えてほしいと思います。
配属リスク、配属ガチャと言った時点で負け。人事制度をハックせよ
──ここまで、総合商社に新卒で入るメリットとデメリットをお話しいただきましたが、商社志望の学生は多いのも事実です。佐藤さんは先ほど「やりたいことを全てやらせてもらえた」とお話ししましたが、そのように働くにはどうすればいいのでしょう。佐藤さんは在職中、いわゆる配属リスクとは無縁だったのでしょうか?
佐藤:語弊を恐れずに言えば、配属リスク、配属ガチャと言ってしまう時点で、自分の情報力や交渉力の弱さを認めているようなものです。
配属も自分から積極的に動けば意外となんとかなりますし、うまく自分のやりたいこと部署を回っている同僚もいました。当たり前のことですが、どの部署だってやる気があって、前向きに自分たちの仕事を語ってくれる人材が欲しいに決まっています。
──それは確かにそうですよね。
佐藤:だから、最初の配属面談では、インターンでベンチャー投資に関わっていたので、短いサイクルで結果が出るトレーディング系の部署に行きたいことや、24時間365日働きまくりたいと思っていることを組み合わせて、石油のトレーディングなどをやりたい、といった話をした記憶があります。
一方で「僕を経理系とか業務系とかに配属すると、なんでこんなヤツをよこしたんだ! って言われるから、本当にやめた方がいいと思いますよ!」と説明しました。その後も希望の部署に行けるように、都度、ルートを見つけ、材料を整理して話をしていました。
──すごい。他の社員の皆さんは、あまりそういうことはしないのでしょうか?
佐藤:商社の中でのキャリアハックはあるんですが、ぶっちゃけ気がついている人は少ないと思います。いい子でいようとする人が多い。「ちゃんとしなくては」という思考が強すぎるんですよ。そうでないと評価されないと思い込んでいるというか……。
会社側は全員がハックしてきたら困るけど、人材ポートフォリオの中に「こういうことをするヤツがいてもいいよね」という枠があって、そこに自分がハマれるなら、積極的に行動すればいいと思います。ただ、商社の中では偉くなれないかもしれませんが。
──いい子でいようとする……そういう人が商社に飼いならされてしまう、商社に喰われてしまう人でもあるのでしょうか。
佐藤:そうですね。中には起業しようと思っている人もいますけど、その多くは「辞める辞める詐欺」で終わります。飲んだときに、辞めるとか、もっとこうするんだとか語る人もいますが、そんな人に限って「もうあと2年」「駐在を経験してから」などと、決断を先送りにすることが多い。
歳を重ねて年収も増え、家族もできて……と時がたてば、どんどん現状維持に心が傾きやすくなるのは明白でしょう。何かやりたいことがあるなら、商社なんてすぐ辞めてチャレンジすればいい。それができない時点で、「牙を抜かれている」と自覚すべきです。
そういう人から相談をお願いされることもありますが、「辞めてから連絡くれれば、本気で相談に乗ります!」と言っています(笑)。
──そうして商社に残り続けた結果、商社でしか通用しない人になってしまうと。
佐藤:これと似た話ですが、学生の皆さんはOB・OG訪問も気を付けてください。話してくれるのは「辞めていない人」でもあるのです。その発言には、会社に適応したというバイアスがかかっているだろうし、何より状況が変わっていくので、皆さんが彼らと同じキャリアを歩めるとは限りません。熱く語られても、ある意味「話半分」くらいで聞くくらいがちょうどいいです。
共同創業者の土屋に起業の話をしたときは、「やりましょう。明日辞めてくればいい?」と言われました。本当にできる人は、いつでも辞められる準備ができているんですよね。そのためには、常に自信がある仕事をしていなきゃいけないし、お金だってある程度ためておかなきゃいけないんです。
──社外でも通用する人は、常に自らのキャリアを意識した行動をしていると。商社に喰われないためには、どうすればいいのでしょう。
佐藤:違和感や憤りを大切にすることだと思います。おかしいことに対して、素直に「おかしい」と言うにはパワーがいるんですよね。狂気と言ってもいい。
違和感を違和感として捉え、頭から離れなくなるまで考える能力は、教えられてできるものではない。だから、もし違和感や憤りを感じることがあったら、「絶対に会社に飼い慣らされない」という強い意志を持ってほしいです。その意志は誰もが持っているものではなく、才能とも言えるものなので。
キャリアのハンドルを放すな。いつでも自分で人生をドライブしよう
──佐藤さんが2020年現在に就活をする学生なら、どういった企業を目指しますか?
佐藤:そうですね。僕が就職活動をしていた15年前とは世の中が変わってきています。今なら30〜50人くらいで、かつ成長をしているベンチャーを選ぶと思います。
例えば、メルカリやDeNAの初期メンバーだとしたら、5年間で得られる成長や経験は、大企業で経験するレベルとは大きく異なるはず。商社マンになってコリドー(※)で楽しむのもいいけれど、そんなもんすぐに飽きますよ(笑)。
(※)……東京・銀座のコリドー街のこと。会社員が集まるナンパの名所
──最近では、ベンチャーで長期インターンをする学生も増えてきていますが、その点はいかがでしょう。
佐藤:いいことだと思います。Shippioにも長期インターンをしている学生はいます。
私のところでは最低半年以上、できれば1年で週3〜4日という条件を出しています。逆にいうと1dayのような短期では、あまり意味がないのかなと。大学で勉強しているならいいですが、もし、勉強しないで遊んでいるなら、インターンくらいしたほうがいいよと勧めています。
──佐藤さんのところでは、どんなことが学べるのでしょうか?
佐藤:うちは仕事の基本を教えています。電話のかけかたとか、リサーチの仕方、文章や資料のまとめ方とかです。歴代のインターン卒業生は、総合商社や大手広告代理店、コンサル、会社経営などその後の進路はさまざまですが、うちで仕事の基礎をフルインストールしてるから、彼らが新卒入社した各社からは、研修料金をもらいたいくらい(笑)。
──インターンの後に、そのまま残ってほしいと思いませんか?
佐藤:そのまま残ってくれてもいいし、大企業に行くのもいいと思っています。少なくとも一度スタートアップを見ておいて、大企業に就職したら、スピード感や熱量の面で「物足りない」と思うかもしれません。そうしたら戻ってくればいいと思いますし、本人の納得感が大事です。5年後に戻ってくるでもいいと思っています。
──ありがとうございました。では、最後に学生たちへのメッセージをお願いします。
佐藤:キャリアについては答えがないからこそ、考え抜いて行動することが全てだと思います。日本でも人材の流動性が上がっており、商社に入社してもそこで一生働くという人は減っています。だからこそ、自分で考えて行動することの重要性が高まっていて、そのときのための準備を今からしておく必要があるでしょう。
今、ものすごいスピードで時代は変わっています。その変化を感じながら、「今、総合商社でいいのか」という視点で各社を見てみてください。その先に、考え抜いた上で納得のいく選択ができればいいと思います。
それから、入社をしても「自分の人生やキャリアのハンドルを離さない」というのも、本当に重要なことです。会社に左右されてしまう人生より、自分の力で行きたい場所を決められる方が、人生はきっと楽しいはずですから。
特集「転職時代になぜ商社」も同時連載中
本特集「商社を喰うか、喰われるか」では、総合商社を離れた立場から、商社にまつわる「ぶっちゃけ話」やキャリア観を聞いています。しかし、これはあくまで総合商社を見る一つの視点に過ぎません。
ワンキャリア2020年の「商社特集」は、二つの側面で記事を展開しています。もう一方の特集「転職時代になぜ商社」では、総合商社社員の「商社で働き続ける理由」に迫っています。こちらの特集もぜひご覧ください。
・【総合商社特集スタート】転職ありきの時代、ファーストキャリアに総合商社を選ぶ意味とは?
▼【特集:「商社を喰うか、喰われるか」】の他記事はこちら
・ヒマラヤ登頂が認められずに新卒3年目で辞めた男が、それでも三菱商事に感謝している理由
・ビビリの僕が、双日を辞めて起業するまで。自分の「プライド」を崩し続けた3年間
・「伊藤忠の魅力」の前に霞んだ起業家精神──気鋭のYouTube事業家が、就活生に絶対に伝えておきたいこと
・三菱商事歴28年商社マンの決断。大企業の経営人材が選んだ「キャリアへのこだわり」
・起業したいなら、商社は「2社目」がちょうどいい──双日出身社長が語る「中継ぎの商社論」
・三井物産出身の起業家が断言「今、商社に行く学生はセンスがない」
▼Shippioの企業サイトはこちら
【執筆協力:yalesna】
(Photo:Rawpixel.com/Shutterstock.com)